Tansa Schoolの一環で8月28日、元ニューヨーク・タイムズ東京支局長のマーティン・ファクラーさんを招いて研修会を開いた。テーマは「どうやってNYタイムズはV字回復を果たしたか」。10年ほど前まで、ニューヨーク・タイムズは破綻の危機にあった。それが今や有料購読者が1000万人を超える。この過程をニューヨーク・タイムズの一員として体験したファクラーさんから、成長の秘訣を伝授してもらおうというわけだ。
ファクラーさんとは10年来の付き合いだ。時には酒を酌み交わしながら随分と語り合ってきたが、今改めてファクラーさんの言葉に耳を傾けると気づかされることが多い。目から鱗だった。
日本ではこの10年で、新聞の部数が1530万部減った。「マスコミ体制」は崩れようとしている。私自身は朝日新聞を退職し、Tansa(当時ワセダクロニクル)を立ち上げて5年半が経った。そうした環境の激変が、ファクラーさんの話を吸収する構えを私に持たせたのだろう。
支局員の解雇から始まった仕事
ニューヨーク・タイムズがいかに経営危機にあったか。タイムズスクエアの近くに新しく建てた本社ビルを、お金がなくて売ったというエピソードが象徴的だ。売却した上で、自分たちは家賃を払って入居したという。
ファクラーさんも経営難のあおりを体験する。2009年に東京支局長に就任した際、最初の仕事はスタッフ3人を解雇することだったのだ。「人を解雇するのは、戦争の次くらいに辛いものだ」とファクラーさん。
しかし、ここからニューヨーク・タイムズは脱皮していく。
ニューヨーク・タイムズの編集主幹であるジル・エイブラムソンさんが、ある目標を掲げたのだ。編集主幹は編集部門の責任者で、エイブラムソンさんは2011年にニューヨーク・タイムズでは女性として初めてその任に就いていた。
目標とは、当時は9割が新聞からの収入、1割がデジタルからの収入だったのを「2020年には全てデジタルからの収入で編集経費を賄えるようにする」というものだった。ファクラーさんいわく「ネットでも記事を出している新聞社」ではなく、「新聞も発行しているネットメディア」を目指すものだ。
この目標のもと、エイブラムソンさんは社内のジャーナリストたちを集めて、「君たちの将来をみんなで考えて新しいアイディアを出しなさい」と指示する。ファクラーさんも参加した。アイデアは4つのレポートとして結実。社内で共有し、実行していく。
2014年 『Digital innovation report』
2015年 『Our path forward』
2017年 『Journalism that stand apart』
2018年 『Mobile first』
オンリーワンの報道を
改革を実行する際にニューヨーク・タイムズが大切にした考え方で、私が興味深かったのは以下の3つだ。
①記者の姿が見える記事を読者は求めている。以前は記事中に「私」が出てくるのは御法度だったが、今は「私」が不在の記事は信用もされない。
②トランプ氏のように大統領でも嘘をつき、それがSNSで拡散するような時代だからこそ、ジャーナリズムが求められている。
③読者は馬鹿じゃない。オンリーワンの報道を求めている。発表されたことをそのまま書く「記者クラブ報道」と違い、探査報道はオンリーワンのコンテンツである。
ニューヨーク・タイムズが躍進したのは、スマホで読まれることを前提にしたコンテンツ作りを徹底していることや、米国発のニュース需要に支えられ海外の購読者が4分の1ほどいることも大きいだろう。
しかし、ジャーナリズムの使命を自立した個人が果たすという原点回帰が最大の成功要因ではないだろうか。
社屋を売っても戦えるか?
結局はジャーナリズムを貫く覚悟が問われているのである。
私が力を得たニューヨーク・タイムズのエピソードがある。ジャーナリストの魚住昭さんが、週刊現代2014年10月11日号の『わき道をゆく』というコラムの中で紹介している。
新聞が社会を救うことがある。その最たる例がベトナム戦争中のニューヨーク・タイムズだろう。同紙は’71年、米国防総省の秘密報告書の全容を暴いた。報告書は、ホワイトハウスがベトナム戦争をめぐっていかに真実をねじ曲げてきたかを物語る第一級の資料だった。タイムズの報道は戦争終結(’75年)に大きく貢献した。
杉山隆男さんの『メディアの興亡』(文藝春秋刊)によると、この歴史的スクープを放ったニューヨーク・タイムズの記者ニール・シーハンが来日した際、ある元記者がこんな趣旨の質問をしたそうだ。
「いくらニューヨーク・タイムズでも、そうした重大な、会社を危機に引きずりこむかもしれない記事をのせようという時は、やはり会議にかけるんでしょうね」
「いや、会議なんて、そんな大げさなものはありません」
シーハンは笑って答えた。
「あの時は、ぼくが副社長のジェームズ・レストンに呼ばれて、社長もいるところで例の秘密文書について話を聞かれただけです」
「レストンはどう言ったのですか」
「ひと言、これは本物か。ぼくが、本物です、と言ったら、レストンは、わかった、と言って(中略)部長会を開いて一席ぶちました。これからタイムズは政府と戦う。かなりの圧力が予想される。財政的にもピンチになるかもしれない。しかし、そうなったら輪転機を2階にあげて社屋の1階を売りに出す。それでも金が足りなければ今度は輪転機を3階にあげて2階を売る。まだ金が必要というなら社屋の各階を売りに出していく。そして最後、最上階の14階にまで輪転機をあげるような事態になっても、それでもタイムズは戦う」
コラムが書かれた当時は、朝日新聞が「原発吉田調書」の記事を取り消した直後だ。社の上層部が勝手に萎縮し、組織防衛に走った結果だった。私は特報部の同僚たちと共にこのコラムを読んで、ニューヨーク・タイムズのエピソードに感銘を受けた。魚住さんは「苦境に陥っている朝日の記者たちに言いたい」と次のようにコラムを結んでいる。
ピンチは必ずチャンスに変えられる。そのことを信じて、批判を恐れるな。ひるむな。萎縮するな。社屋を売っても「タイムズは政府と戦う」というレストンの言葉を忘れないでほしい。
その後、私はワセダクロニクルを立ち上げた。「ピンチ」を、非営利独立の探査報道組織の設立という「チャンス」に変えることができた。別件の取材で魚住さんと会う機会があり、コラムで応援してくれたことに御礼を伝えた。
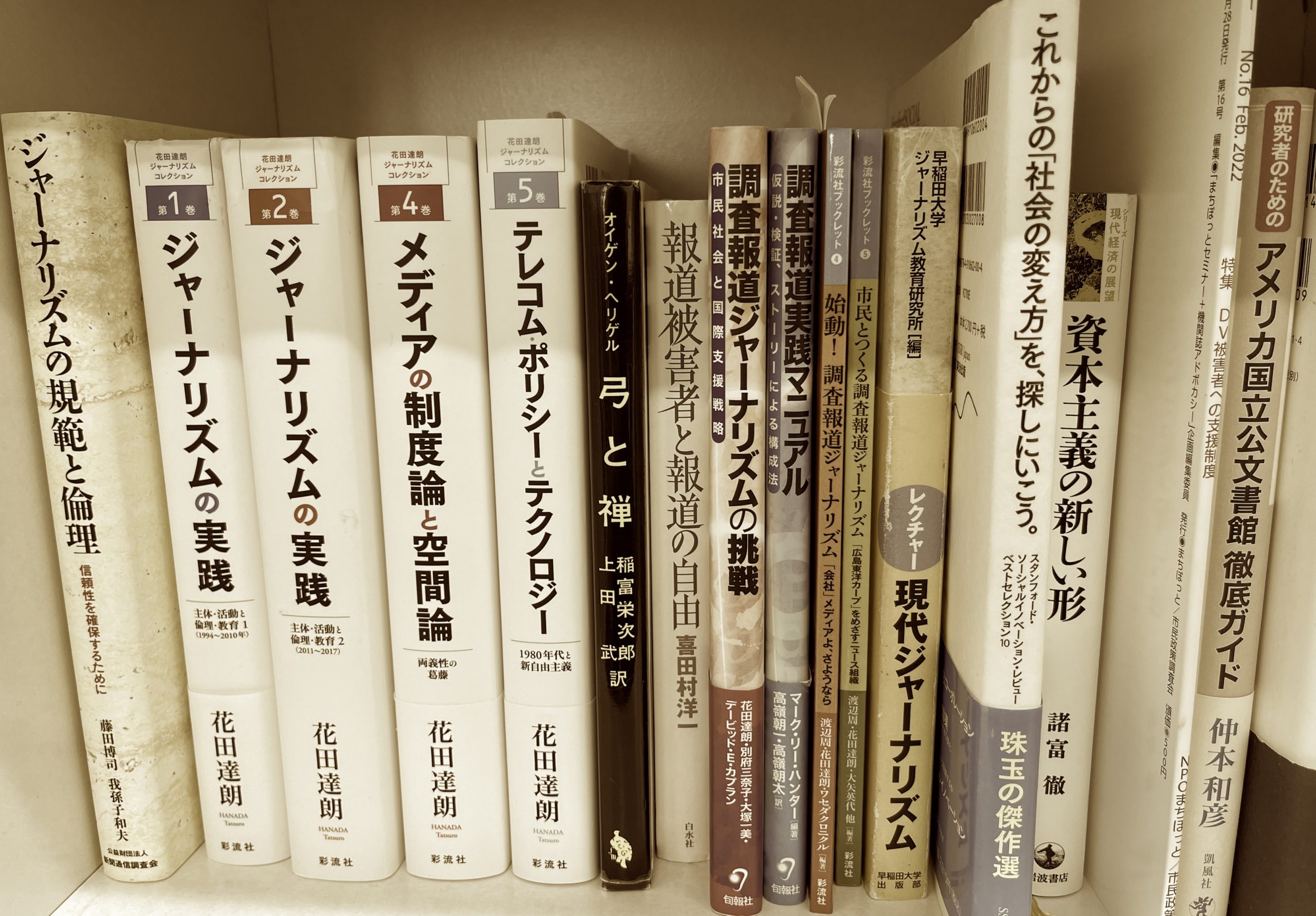

 メルマガ登録
メルマガ登録