
私は大学卒業後、保育園の栄養士として就職した。0才から5才の園児が200人ほど通う園だった。
園長は、床が傷つくからという理由で、体育館で縄跳びをすることを禁じるような人だった。
新人職員が少しでもミスをすると気が済むまで説教をし、指導がなっていないと主任の保育士たちを叱った。
主任の保育士たちは、園長を怒らせまいと新人保育士が直接園長と話すことを禁じた。私を含め、3人いた新卒入社の栄養士も同様だ。私が勤務していた2年間、許可なしに園長と話したことは一度もなかった。
行事となると、園長の指導はさらに厳しくなる。保育士も園長の指導通りに子どもたちをコントロールしようと必死だった。子どもに向かって怒鳴ることは頻繁にあった。
秋の恒例行事である発表会の練習に参加していた時のことだ。発表会では、舞台上で竹馬やフラフープ、跳び箱などを使い、曲に合わせて竹馬に乗りながら隊形移動をしたり、跳び箱を飛んだりする。私は舞台で使う道具の出し入れを手伝っていた。
この日は本番直前で、0才児から5才児のリハーサルが朝から夕方まで行われていた。5才児クラスの発表は特に大変だ。50人と園児数も多く、1人の出番は2、3回あった。
舞台道具の出し入れも、1つ間違えると園長から注意が入る。
プレッシャーを感じながら、私が舞台の袖で待機していた時のことだ。竹馬から落ちてしまった子が1人いた。すぐに乗り直したので問題ないと思ったが、前で見ていた保育士は違った。その子に向かって怒鳴った。
怒鳴られた子は、舞台袖にいた私のもとへ戻って来るなり言った。
「もう練習したくない。しんどい」
その子は号泣し始めた。とりあえず落ち着かせようと、私は声をかけながら背中をさすった。
ところがそこへ、さっき怒鳴ったのとは別の保育士がやってきて、その様子を目にするなり「何してるの、早く次の準備しなさい!」と言い、その子どもの背中を手で押した。
だが私は、無理やり連れて行かれるその子を、ただ見届けることしかできなかった。当時、度重なる同期の急な退職や日々の人間関係に疲れ、私も精神的にギリギリの状態だったからだ。一番仲の良かった栄養士の同期はパニック障害に陥り、ある日突然出勤できなくなった。
秋の発表会で起きたような出来事は日常的にあり、私は友達によく相談していた。友達から返ってくるのは「優香が精神的にまいってしまう前に、その保育園を辞めた方がいい」というアドバイス。私はその言葉に助けられた思いがして、保育園を退職した。
それから4年間、別の保育園での勤務やデンマークへの留学を経験し、今年の3月からTansaでジャーナリストとしての道を歩み始めた。
Tansaに入って初めて手がけているテーマが、農薬のネオニコチノイドの問題。農薬会社や農水省、農協や自民党の政治家など、私がこれまでに出くわしたことのないような大きくて強い相手だ。取材ではいつも戸惑っている。
ペンギンコラム第5回に書いた、農林水産省への情報公開はまだ開示されていない。あれから野村哲郎・農水大臣に情報公開にちゃんと対応するよう抗議文を送ったが、担当課の対応は頑なになるばかり。それでも編集長の渡辺は「引き下がらず、もう一回相手にメールを送ってみて」などと言ってくる。
正直、しんどいなと思う時はある。それでも、このテーマを頑張れるのはネオニコという農薬が子どもの発達に影響があると世界中の科学者が指摘しているからだ。私は、あの時の保育園の子どもたちの顔を思い浮かべながら取材をしている。
舞台袖の悔しい経験を二度としたくない。
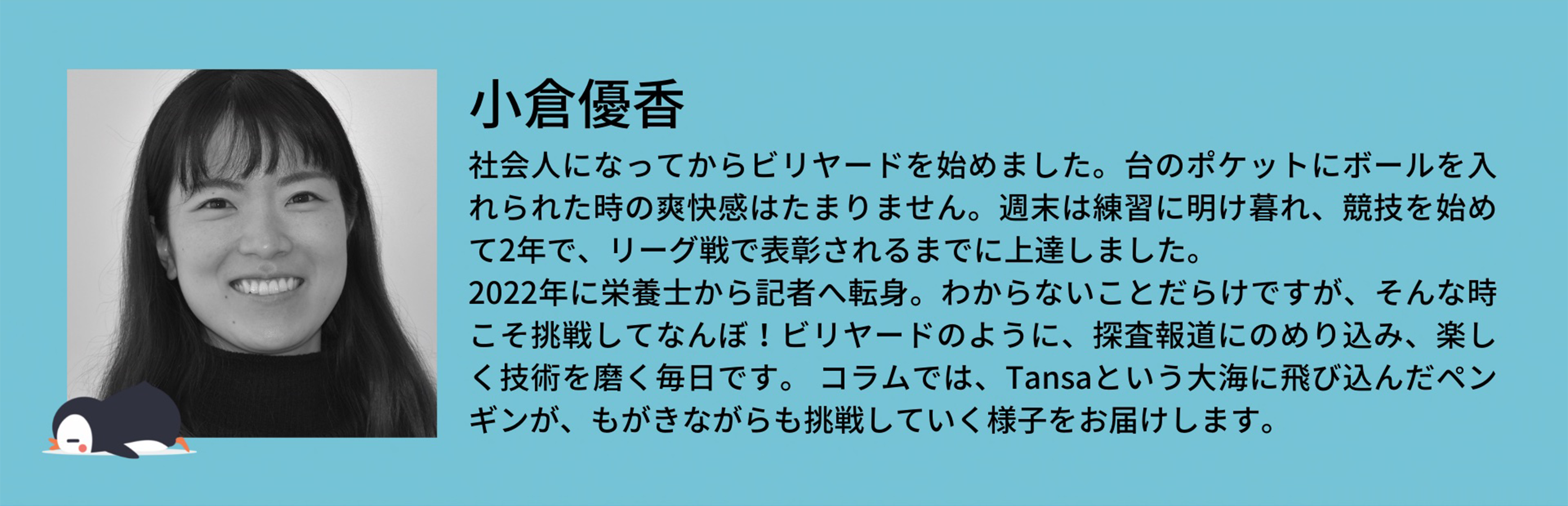

 メルマガ登録
メルマガ登録