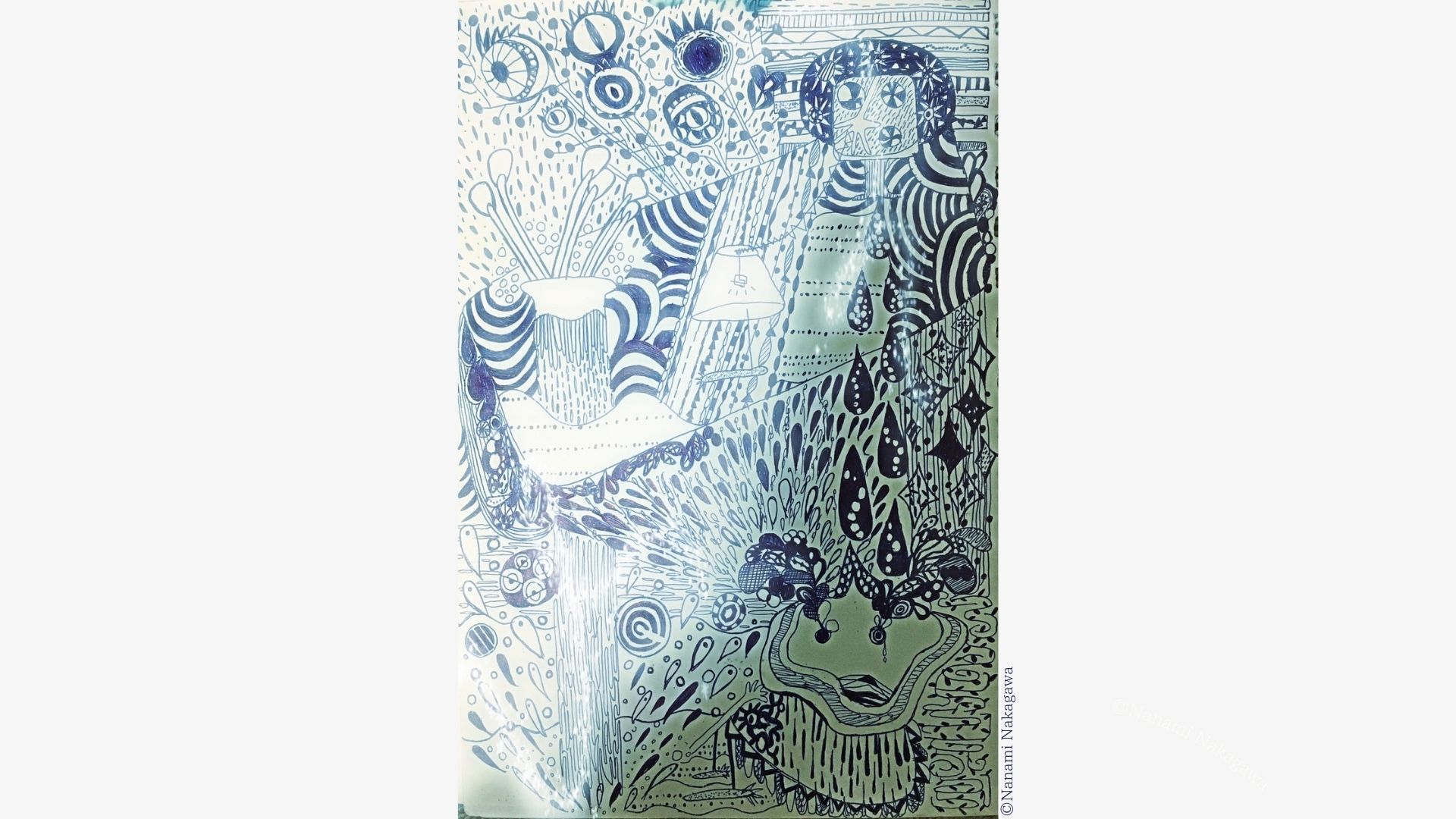
私は3月7日、産業労働組合「関生支部」を警察・検察が大弾圧/検察「どんどん削っていく」/大阪高裁では逆転無罪「憲法28条で保障された正当な行為」をリリースした。
警察と検察が、関生支部のことを犯罪者扱いすることがいかに的外れで横暴か。そのことを私が確信したのは、関生支部メンバーの松尾聖子さんを取材したことが大きい。
24年前、松尾さんは26歳でシングルマザーだった。1歳半から5歳の幼い娘3人を養うため、ミキサー車の運転手になることを決めた。日雇いで働いたり、時には自身の親に子どもの世話を頼んだりしながら、なんとか子どもたちを育て上げた。
松尾さんに、私は母の姿を重ねた。
母は23歳で私を産んで以来、ずっと働いている。今は派遣社員で、時給制・週5日勤務の医療事務だ。手取りは月20万円に満たない。ボーナスもない。一時期は、日中は医療事務、夜から翌朝にかけては介護の仕事を掛け持ちしていた。家族の事情があり、母が私と3歳下の妹を育てるために身を粉にして踏ん張った。
一昨年、母から連絡がきた。
「派遣会社から、20年勤続の表彰で商品券20万円分をもらった」
母は喜んでいたのかもしれないが、私は驚いた。母は20年間、ボーナスもなく時給制で働き続けてきた。職場から頼まれれば、毎日でも残業した。それでも20万円分の商品券しか支給しないなんて、あまりに母に報いていない。
だがこれが、今の日本の実情だ。今年の春闘は、賃上げ要求に対する満額回答が多いとニュースになっているが、その恩恵を受けるのは多くが大企業の正社員。4割に上る非正規労働者の暮らしは苦しい。年間給与の平均額は30年前から30万円減った。
日雇いの運転手だった松尾さんを、関生支部は正社員にまで押し上げた。一部の大企業の正社員しか優遇されない日本社会にあって、これは希望だと私は思う。
ところが、不思議なことにほとんどのマスコミは関生への弾圧事件を取り上げない。取り上げても警察と検察の肩を持つような内容だ。
理由を考えた時にまず思い浮かんだのが、権力との癒着だ。警察や検察を担当する記者は、記者クラブを舞台に両者と仲良くなって、明日わかることを今日報じる競争に明け暮れている。対立して情報をもらえなくなるのが怖いのではないかという理由だ。
ただ、それよりも大きな理由があると思う。弱い立場に追い込まれている人の気持ちがわからないし、わからないから本気で怒っていないのだ。いち早く当局の情報を報じて社内で褒められたいという気持ちがあったとしても、それを理不尽への怒りが上回れば、警察や検察の側ではなく、関生支部の側に立つのではないか。
今思えば、本質は同じだといえる出来事は過去にもあった。
認知症や目が不自由なお年寄りに新聞を押し売りする「高齢者狙う新聞販売」で、新聞労連を取材した時のことだ。新聞労連は各新聞社の労働組合の連合体だ。自分たちが糧を得ている商品をめぐり、犯罪ともいえる所業が行われていることに、新聞業界全体の問題として労組が声明を出すのではないかと私と編集長の渡辺周は期待した。
これに対して、当時の吉永磨美委員長(毎日新聞)の歯切れは悪かった。結局、今も声明は出していない。業界全体のために闘い続ける関生支部とは対照的だ。
私は当時、新聞労連の幹部たちは数年で所属する社に戻ることを考えて、雇用主と事を構えたくないという気持ちがあるのだと考えた。
しかし根本は、新聞の押し売りへの新聞労連の態度も、窮地に立つ人への想像力の欠如が原因だと思う。
Empathyという言葉がある。
私が大学生のとき、国際NGO「Ashoka」でインターンをしていた際にこの言葉を知った。Ashokaは、社会にある喫緊の課題を解決するために、問題を生みだす構造に切り込み、事態を根本から変えるイノベーターを世界各国で発掘・支援している。イノベーターの選考基準の一つが、Empathyだ。
Empathyは「共感」と日本語訳されることが多いが、私はもっと深い意味を持っていると思う。たとえば、Ashokaのスタッフやイノベーターたちは、「自分と相手の肺を重ねるように、相手の呼吸に合わせようとすること」、「他者の靴を履くのを想像して、その人の歩幅を感じ取ろうとすること」と解釈した。
ジャーナリストにとっても、Empathyは必要不可欠だ。
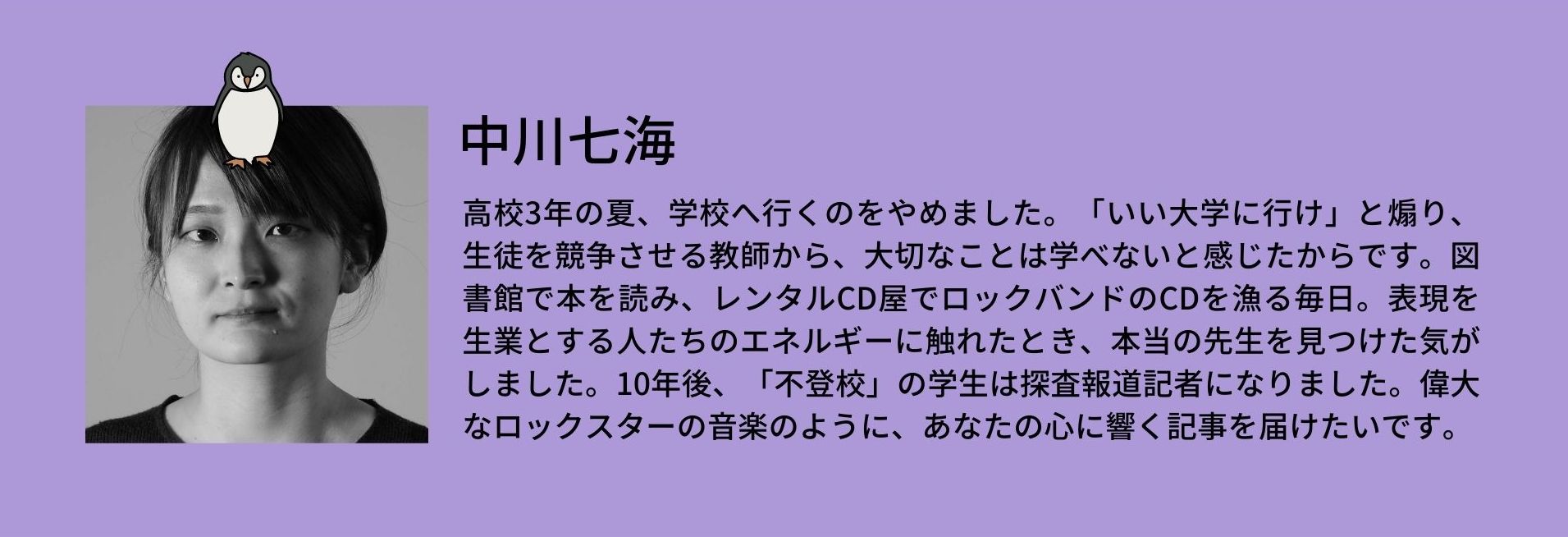

 メルマガ登録
メルマガ登録