福浦勇斗(はやと)の遺族である母のさおりは夫の大助と連名で、共同通信に対して意見書を提出した。
勇斗の自殺事件を追った石川陽一の著書『いじめの聖域』の第11章を共同通信が問題視し、石川を追及するための審査委員会を設置したことを知ったからだ。
第11章では、長崎新聞の報道姿勢に対する批判を展開している。さおりはそれらの批判が正当であることを、一つ一つ、根拠を示しながら主張していく。
まずは「地元メディアは黙殺」という表現の妥当性から論じた。
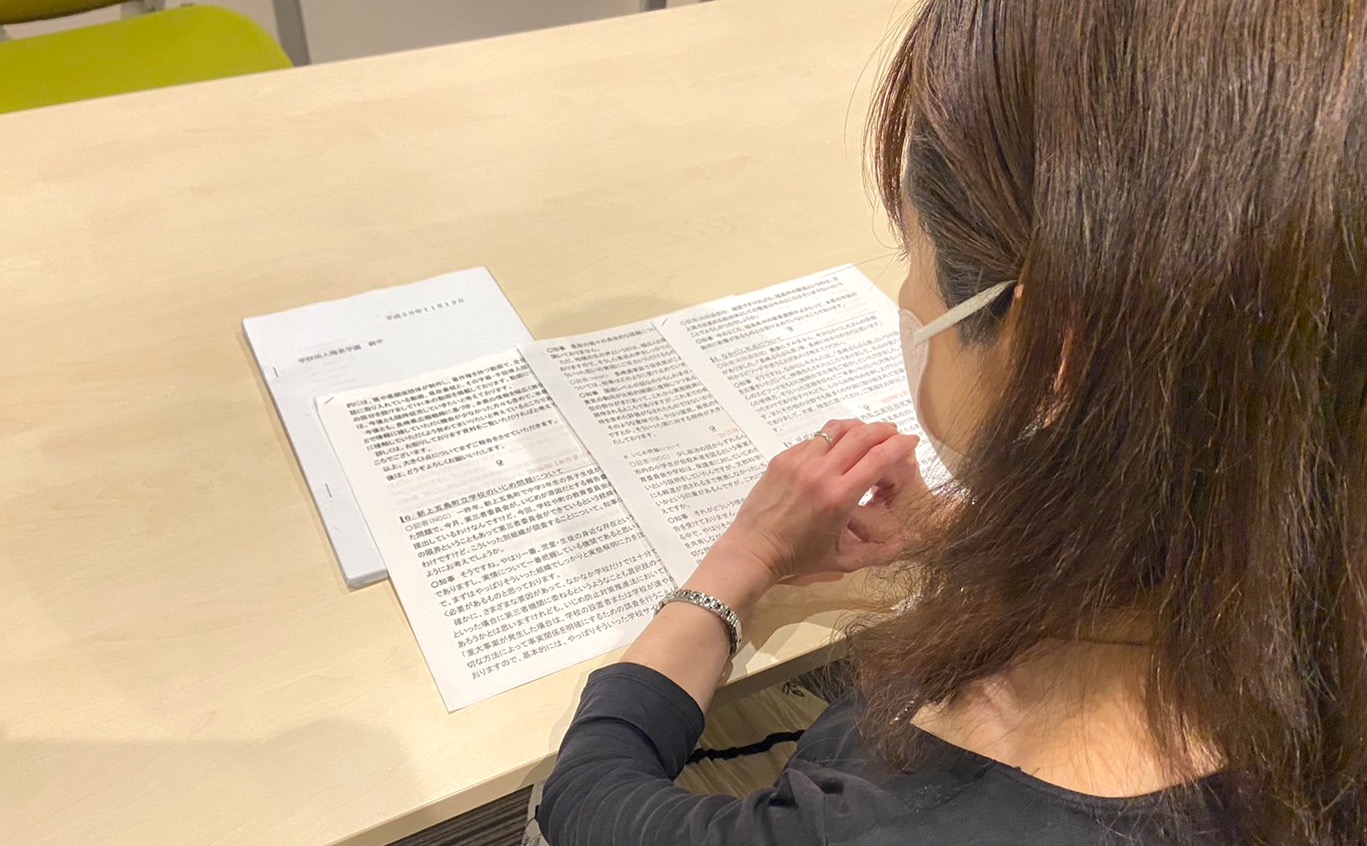
福浦さおりさん=2023年6月8日、中川七海撮影
審査委員会「論評の範疇を超えた論理の飛躍」
審査委員会は2022年12月14日の石川宛ての文書で、審査を行う理由について次のように記している。
「審査委員会としては、『いじめの聖域』の第11章『責任から逃れたい大人たち』全般において、十分な裏取り取材がされておらず、論評の範疇を超えた論理の飛躍の疑いがある」
その上で、「特に問題と考えている」箇所をいくつか示した。
一つ目が、長崎新聞のある行為を「黙殺」と表現したことだ。
2020年11月17日、石川は「海星高が自殺を『突然死』に偽装/長崎県も追認、国指針違反の疑い」と共同通信から報じた。
勇斗が自殺した後、海星学園は遺族に対して、対外的には自殺ではなく「突然死」と説明することを提案した。とうてい遺族には受け入れられない。だがその提案を、長崎県の総務部学事振興課参事の松尾修が追認していた。
石川の記事は反響を呼んだ。記事を配信したその日、Yahoo!ニュースはトップページに掲載し、翌日の朝刊では東京新聞の社会面トップを含む少なくとも長崎県外の15紙が報じた。
ところが、長崎県内で最もシェアが高い長崎新聞は全く報じなかった。これらの事実を根拠に、石川は一連の出来事を「地元では無視された格好になった」と表現し、小見出しに「地元メディアは黙殺」とつけた。
「批判の矛先が行政となるとためらいか」
さおりは、石川が「黙殺」と表現することに何の問題があるのか、二つの点で理解できなかった。
一つは、長崎新聞が報じなかった石川の記事内容は、重大な事実の暴露である点だ。遺族が石川に提供した録音データに基づいている。
重大で証拠もある事実だからこそ、それを取り上げないことを「黙殺」と表現することは妥当だ。
私たちは、学校や長崎県とのやり取りを録音していましたが、このことは長いこと伏せていました。なぜ公にしなかったのか、それは司法が最後の砦と考えていたからです。
司法の場でしかこの録音データを明かさないと決めていた私たちが、御社の石川記者の熱心で誠実な姿勢に接し、この方に録音データのことを託してみたいと思うようになりました。
石川記者は、録音データを基にこの日、記事を出しています。内容は本にも書かれている通り、学校が私たちに提案した子どもの死を突然死にできる、という発言を県の職員が追認した件です。
もう一つは、他メディアが石川の記事内容を取り上げて騒然とする中、地元の長崎新聞が何も触れなかったことの異常性だ。
録音データという証拠が存在することすら誰も知らなかったこともあり、この新たな真実はインターネット上では、大変な騒ぎとなりました。
現に、記事の配信がおこなわれた直後から、私たちには地元の報道機関から電話の問い合わせがありました。その中には当然、長崎新聞も含まれていました。その日の夕方の18時50分頃のニュースでこの第一報を放映したテレビ局もあったほどです。反響の手ごたえを感じていたこともあり、当然のことながら、翌日の朝刊にはこの話題が掲載されるとばかり思っていました。
ところが、翌日の県内の新聞のどこを見てもこの話題について掲載している社はありませんでした。他県の新聞では掲載されていたようで、その新聞社がインターネット上でも記事を出していることで、県外での状況がわかりました。
他県では、問題視されている県の職員の対応が、なぜ長崎県内では取り上げられないのか、私たちには理解できませんでした。遺族と学校の対立は広く報道されるのに、批判の矛先が行政となるとためらいがあるのだろうか、と不安になりました。
後に県の新任の担当者から聞いた事でありますが、私たちの疑問や不安をよそに、その頃、既に県には苦情の電話が全国から殺到していたそうです。
さおりは、石川が「地元メディアは黙殺」と書いたことは、その通りだと結論づける。
この事実を、石川記者が「地元メディアは黙殺」と書いたことに対して、審査委員会は異議を唱えているようですが、私たち遺族としては、この言葉通りだと思っています。
私たち遺族が明かした真実が、インターネット上では炎上し、県外では多くの新聞の紙面に掲載されたにも関わらず、県内の新聞社には受け入れられなかった時の遺族の葛藤をご理解頂けないでしょうか。
=つづく
(敬称略)
保身の代償 ~長崎高2いじめ自殺と大人たち~一覧へ
 メルマガ登録
メルマガ登録